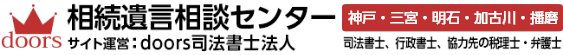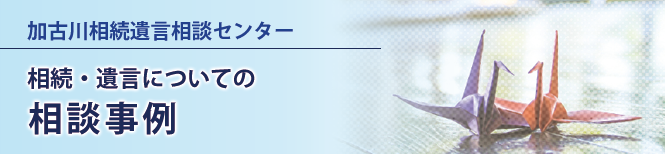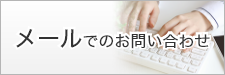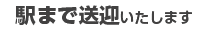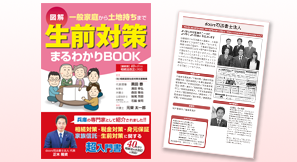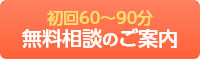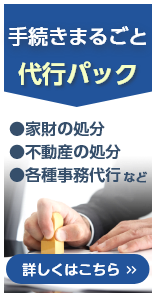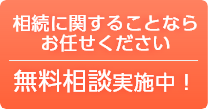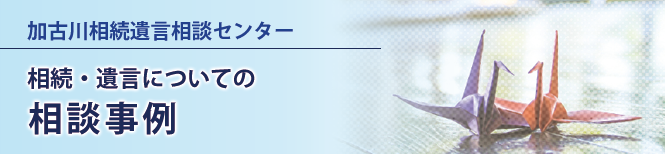
地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 28
2018年06月06日
元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(加古川)
離婚した元夫の父親が亡くなったことを知りました。 離婚した際、二人いた子供は私が引き取りましたが、元夫の父親とは間違いなく血がつながっています。この場合、私や子供に相続する権利はありますか?
配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。
まず、ご相談者様には法定相続人としての相続権はありません。(遺言書で相談者様へ相続させる旨が記されている場合は別です)
結婚すると義理の両親を「お父さん、お母さん」と呼ぶようになることがあるので、配偶者の親の遺産を相続できると考える方もいらっしゃいますが、婚姻関係によって結婚相手の親に対する相続権が発生することはありません。法律上、結婚は夫婦間で婚姻関係のみが結ばれ、相手の親との親子関係が結ばれるわけではないのです。親子関係を結ぶには、養子になるしかありません。
次に、被相続人の孫にあたるお子様たちですが、こちらは相続人になれる権利はあります。 子供の相続権は両親の離婚によって失われることはありません。ただし、孫が相続する場合は代襲相続となりますので注意してください。
つまり、元旦那様がすでに亡くなっているか、何らかの理由で廃除や欠格によって相続権を失っていない限り、ご相談者様のお子様が相続人となることはありません。(こちらも、遺言書でお子様に相続させる旨が記されている場合はその限りではありません)
上記の理由でご相談者様のお子様が相続人である場合、遺産の配分は被相続人の配偶者(この場合元旦那様のお母様)が存命かそうでないか、被相続人の子供(元旦那様のご兄弟)が何人いるかによって変わってきます。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。 ご相談者様のお子様は二人ですから、元旦那様の代襲相続分をさらに二人で分けることになります。
加古川市にお住まいでしたらぜひ一度、当センターの播磨事務所の無料相談にて詳しいお話をお伺いできればと思います。
2018年05月08日
Q:相続の手続きは自分でも出来ますか?(稲美町)
稲美町の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので、相続人は私と弟の二人です。一緒に生活をしていた長女の私が手続きをする事になりますが、遺産としては実家と預金が少しなので自分で手続きが進められるのではないかと思いますが、専門家に依頼しなくても出来るものなのでしょうか?(稲美町)
A:相続のお手続きはご自身で行う事も可能です。
ご自身で相続手続きを完了させる事は可能です。しかし、相続手続きには期限のあるものもありますので注意して手続きを進める必要があります。稲美町で一緒に暮らしていたという事なので、預金については把握しているかもしれませんが、もし負債があった場合には相続放棄をするという事が必要になるかもしれません。この相続放棄の手続きに期限があり、被相続人が亡くなった事を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをしなければなりません。ですので、この3ヶ月以内に財産についての調査を終わらせておかなければならないのです。
また、相続人は姉弟だけとの事ですが、不動産の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、亡くなったお母様の戸籍と相続人の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。
目安として、相続人の調査と相続財産の調査を3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などへの調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続放棄をするとなると、家庭裁判所への手続きも必要となり、一般の方には難しい内容になります。
私ども相続遺言相談センターは、相続の専門家ですので、今回のような相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進める事が可能でございます。稲美町での相続のお手伝いは、ぜひ加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお任せ下さい。
2018年04月16日
Q:祖母の介護をしていた母は多く遺産をもらうべきでは?(播磨)
私の母は播磨町で祖母の介護をしながら生活しています。祖母本人の希望もあり、自宅での介護生活が続いていますが、母の負担はとても大きいものがあります。母には弟が一人いますが、介護の手伝いをしてくれたことはありませんし、感謝やねぎらいの言葉もありません。このような状況でも祖母が亡くなった時の遺産分割は姉弟で同額ずつになるのでしょうか? 母はお金に無頓着なのですが客観的にみて不公平な気がします。祖母の介護を一手に引き受けた母は弟よりも多く遺産をもらうべきではないでしょうか。祖父は数年前に他界しています。(播磨)
A:相続人間の不公平を解消するための制度があります
今回のケースでは、相続人となるお母様は被相続人となるおばあ様の介護で、被相続人の財産の減少を防いだと言えます。もしお母さまが介護をしていなかったら、介護施設などに支払う介護費用が必要だったからです。このように被相続人の財産を増やすこと(または減少を防ぐこと)に貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。お母さまは遺産分割の際に寄与分を請求することができるでしょう。
または、おばあ様の認知能力に問題がなく、おばあ様にその意思があれば、遺言書を作成し、お母様の寄与分を考慮した遺産分割をできるようにすることも可能です。
原則として寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。
事前にできる準備はなにか、いざ相続が起きたときになにができるかを考えておきましょう。ただ相続には専門的な知識が必要な場面が多々あります。わからないことや不安な点があればぜひ加古川相続遺言相談センターにお電話ください。初回無料相談で相続の専門家が豊富な経験を活かしたご提案をさせていただきます。
28 / 30«...1020...2627282930»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
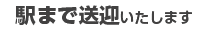
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。